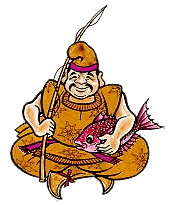 西宮エビスは丹後の泣きエビス 46三浜
西宮エビスは丹後の泣きエビス 46三浜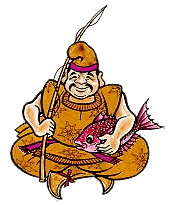 西宮エビスは丹後の泣きエビス 46三浜
西宮エビスは丹後の泣きエビス 46三浜
![]() 三浜の浜は砂地で、波がうちよせては美しい砂
三浜の浜は砂地で、波がうちよせては美しい砂
![]()
むかしむかし、三浜に幸助さんという人が住んでいました。若いころ は体が弱く、よく父母に心配をかけました。漁師になるころから自分の体に気を使い、毎朝健康のため浜を歩くことにした。
ある朝のことでした。幸助さんはいつもの様に浜をあるいていました。朝日で砂はキラキラと光っています。ふと先の方に光り
「ほう、こりゃエビス様だ、なかなかりっぱなもんだなあ」
幸助さんは、話に聞いていたエビス様を手にするの初めてでした。「これは、これはもったいない」幸助さんは、両手で持ち上げ、抱くようにして家に急ぎ帰りました。家にまつってあげよう。家のかべのそばにおいて見た、やぶれた壁のところではどうにも様にならない。ねていても気になってならない。朝早くおきた幸助さんは、再び両手でだくようにして、村の
そっとエビス様を取り上げ、背おっていた
「丹後へ、三浜へかえりたい」だれか小さい声で言っているようだ。うしろをみてもだれもいない。いそいだ。下りの道だ。少しらくになったので、ゆっくり歩いた。「丹後にかえりたい、丹後にかえりたい」小さい声だが、又きこえた。このあたりは、キツネがよくでるそうだが、再びいそいで歩いた。坂なので、自然に足が早くなる。「丹後へかえりたい、三浜にかえりたい」「ウォ。わしは善人だぞ」といいながら歩いた。だれのいたずらかな。まわりはくらやみで誰もいない。平たいらへついた。海辺の山ぞいに歩いた。つかれてきたが休む気もしない。
「丹後へかえりたい、丹後にかえりたい」声が大きくなった。耳をつむるようにいそいだ。 浜村をこえ、峠をこえ、少し東の空があかるくなった。田辺の町並のあるところにきた。「丹後へかえりたい、丹後にかえりたい」しばらく立ちどまって耳をすました。「丹後にかえりたい」どうも背おっている厨子の中から声がする。そこにすわって厨子の中のエビス様を見た。「ウエン、ウエン」とないている。これはよわったな。とんでもないものをぬすんでしまったものだ。おいよいかげんに泣きゃんでくれ。でも、今更三浜にかえるのも、ぬすびとですというようなものだ。「えい、歩け歩け」と、再び南の方に向かって歩きだした。山こえ、坂こえ歩いた。「丹後にかえりたい、丹後にかえりたい」まだ声はする。
三日間休まず歩いた。やがて
泣きエビス、丹後のエビス。泣きエビス、丹後のエビスさようなら、と歌うようにいった。この歌声をきいた人があるそうである。その後も六部は口ぐせのように、丹後のエビス、泣きエビス、といった。
そのエビス様をまつってある宮が商人がよく参り、ご利やくのあるという、今では世に知られた西宮エビス神社だと。
【六部】広辞苑より
リクブ 時代によって異なるが、唐代では中央行政官庁である尚書省の、吏・戸・礼・兵・刑・工の六部局。 ロクブ〔国〕「六十六部」の略。法華経ホケキョウの行者で、日本全国の国分寺または、一の宮を巡拝した者。江戸時代には、鉦カネをたたいたり、鈴をならしたりして、背に廚子ズシを背負い、家ごとに銭や米をこい歩くようになった。▽書き写した法華経を日本の六十六か国の霊場に各一部ずつ納めたことからいう。